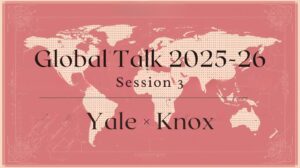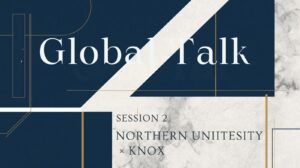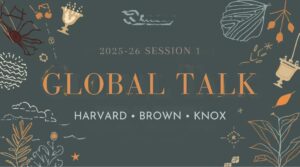私が今回参加したSession23ではUniversity of Massachusetts, Amherstの皆さんと交流を行いました。
取り扱ったトピックは大きく「気候変動について」、「貧富の格差について」、「ナショナリズムについて」で、各トピックに対し1度の同時交流が計3回行われました。
交流の流れは以下の通りで、各トピックごとに②~④を繰り返していきました。
①Knox生とUMass生が混ざった少人数のグループに分かれる。
②各自で各トピックに関する事前学習(課題)に取り組み、日米の現状について知る。
③SNSのグループチャット機能を用い、UMass生からの質問に答える形で軽い情報交換や意見交換を行う。
④同時交流でトピックに関して理解を深め、掘り下げた議論を行う。
(まずグループに分かれてディスカッションを行い、その後全体で話した内容を共有)

トピック1「気候変動について」
主に日本やアメリカにおける気候変動問題に対する政府や企業などの取り組みについてお話ししました。特にグループチャットでの交流の際に話題に上った「気候正義」という言葉は深く心に残っています。あまり日本では浸透していないように感じますが、気候正義とは気候変動によって生じた不平等に責任を持って向き合うという考え方のようです。そして気候正義は不公正が生じることから人権問題としての側面も持っており、被害者側の存在を明確に認識するという点、さらにこの考え方が人種差別と深い関りがあり、訴訟の多い国とも知られるアメリカでは割と知られているという点でとても興味深く感じました。
また同時交流では、新大統領が就任したばかりであったため、政策に関する話も多かったように思います。グループのUMass生、他グループのUMass生ともに大統領の持つ影響力の大きさについて言及しており、環境問題に関して自分の意見をしっかりと持っていることが印象的でした。
トピック2「貧富の格差について」
主に私たち学生の貧困問題をはじめとした身近な場面で見られる貧富の格差についてディスカッションを行いました。アメリカの大学の授業料はとても高いと以前から聞いていましたが、UMass生の皆さんも奨学金を受給したりアルバイトをしたりしているみたいです。日本では両親に学費を払ってもらうことも少なくはないと思いますが、アメリカの大学生は家族の援助なしに大学を卒業する人もかなり多く、自立心の強い人が多いのも国民性かもと聞いて面白く感じました。
またアメリカではホームレスの方も多く見受けられるとの話もあり、日米の街の様子の違いなどについてもお話しし、ホームレスの方の人数の増減やその原因についても考察を行いました。

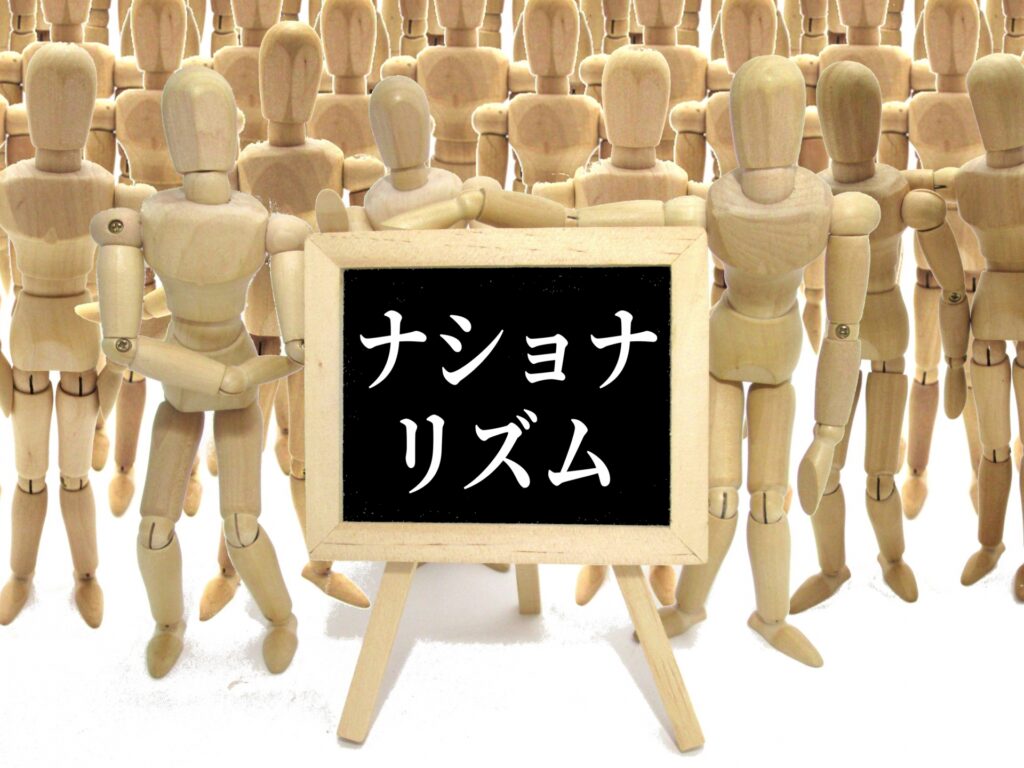
トピック3「ナショナリズムについて」
日本における移民の受け入れや、外国人に対する偏見・差別について話し合いました。日本とアメリカの現状をリサーチしたり比べたりする中で、自国に対する理解も深められたように感じます。特に興味深く感じたのが「日本での生活費の高さを外国人のせいにする傾向があるか」という議題でした。多くの人が様々な原因で近頃の物価高が生まれていることは知っていますが、大都市や観光地ではインバウンドの増加による物価上昇がよく指摘されます。しかし日本では国内に住み生活している人々に対するこういった考えはあまり聞かないことに気づかされました。そして同時交流の際の全体での情報共有でも様々なことを学びました。映画などでは目にすることもありますが、アメリカでは国旗を掲げている家も多いことに驚かされました。また「Diversity(多様性)」、「Equity(公平性)」、「Inclusion(包括性)」をひとまとめにしたDEIという言葉も存在するとのことでした。
今回のSessionは社会問題を主に取り扱ったため、難易度が高く苦戦させられることも多くありました。そもそも事前学習の段階で知らない語彙に出会うこともしばしばでした。またUMass生からの質問を受ける中で、己の自国への理解の低さに愕然とさせられる一方、リサーチやディスカッションを重ねて様々な意見や専門家による分析・指摘にも触れることができ、日米の違いや両国の現状について深く考えるきっかけとなりました。加えて、各グループで話し合ったことの要約を全体に発表するといったこともあり、分かりやすく伝えることの練習にもなったと思います。

本Session参加前はグローバル化した社会で、当たり前に他の国と密接な繋がりがあると認識していましたが、どこか曖昧でアメリカの社会問題を対岸の火事と捉えている部分もあったように思います。しかし同年代の学生同士で互いの現状を比較することによって、アメリカが、そして日本の問題に関しても身近なものとして感じられるようになりました。広い視野を持ち、今後は日本はもちろんのこと世界の時事問題についても積極的に取り入れていきたいです。最後に素敵な実りある交流にしてくれた皆さんに尊敬と感謝です!(Y.H)