2月2日に「アメリカで日本語を教える イエール大学の日本語教育現場から」をテーマに、Global Talk Forum Vol. 8が開催されました!スピーカーは、オハイオ大学大学院言語学部修士課程を修了され、ヴァッサー大学、オレゴン大学、オハイオ大学、オバリン大学を経て、2000年より25年間にわたり、イェール大学にて教鞭をとられていらっしゃる西村裕代先生です。
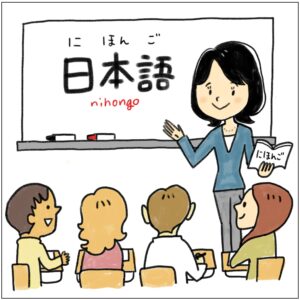 当日は、西村先生が日本語教師になられたきっかけから、イェール大学の日本語プログラムについて、そして日本語教師とは実際どんな職業なのか、また、日本語と英語の違い(日本語は何が難しいのか)を実際西村先生が行っている日本語の授業の様子も見せていただきながらお話をしていただきました。
当日は、西村先生が日本語教師になられたきっかけから、イェール大学の日本語プログラムについて、そして日本語教師とは実際どんな職業なのか、また、日本語と英語の違い(日本語は何が難しいのか)を実際西村先生が行っている日本語の授業の様子も見せていただきながらお話をしていただきました。
なんとなく皆さんも日本語はひらがなやカタカナや漢字もあり、習得するには難しい言語の一つではあるだろうと感じていらっしゃると思いますが、米国外務職員局によると、日本語は英語話者にとって”最高難易度”である「カテゴリー5」に位置しているとのことでした。(一番易しいカテゴリー1に入っているのはスペイン語やイタリア語とのこと)
そして、日本語で「日常的や専門的コミュニケーションにほぼ支障が出ないレベル」に達するために必要な期間は、88週間(2,200時間)。1日3時間休みなく続けたとしても733日、つまり約2年かかるそうです。(しかもこの指標の元になっているのは米国の外交官なので、相当に高い知的レベルや学習コンピテンシーを有している人でも2年かかるということです。)
その最高難易度である日本語を、英語話者の方が0から初級の「日常会話がはなせる」ようになるまでは約300時間、語数1500、漢字300程必要だと言われているところ、大学の4年間、日本語の授業時間を受けた場合は合計約260時間ほどだそうです。ですが、その300時間には及ばない授業時間の中で、むしろ、2ヶ月後には自分の夏休みの思い出をテキストで(ひらがなとカタカナと漢字も含めながら)書いていたり、1.5年後には二組で小噺を披露できるくらいのレベルに成長されている学生さんたちの実際の様子を見させていただき、言語習得するスピードの速さにとにかく驚かされたと同時に、西村先生のお話を伺い、学習者が「予習」に取り組んでいるという点が一つの大事なポイントとなっていると感じました。
要は、予習で、基本文型・語彙・表現を覚えて、活用練習などもしてくることが前提で、授業では、日本語教師がその予習内容を使えるシチュエーション(状況)を作ってあげて、実際に使う相手となり、少しずつこれまで学んだことと新しい語彙や表現や活用を増やしていけるようにしているそうです。(英語を学んでいる私たちも「予習」の時間は、大切にしなければいけないことだなと聞いていて思いました!)今は少しずつ変わってきている部分もあるかもしれませんが、私が学生の頃は、英語の時間(授業時間)はインプットの場(新しい語彙、文法を学ぶ場)で、アウトプットする時間はほとんどなかったように思います。なので、西村先生のお話を聞いて、授業中にアウトプットの機会をたくさん設けること、そのためには、学習者が予習をしてくるというサイクルはどの言語を学ぶ上でも、より良い相乗効果につながるのではないかと思いました。
もちろん、言語に取り組む時間(予習や授業時間や復習時間)以外の言語の教授法もたくさんあり、それらを工夫して取り入れながら、効率的に日本語を学ぶためには、まずは「丁寧体(です、ます)」から入るということも教えていただきました。
個人的に興味深かったのは、学習者の母国語からくる影響(イントネーションやピッチ音など)やルール(例:フランス、イタリア、スペイン語を母国語としている人は”H”を発音しないなど)を幅広く、様々な言語の特徴を知っておく、興味を持つことも日本語を教えるにあたっては大切なことだと知れたことです。
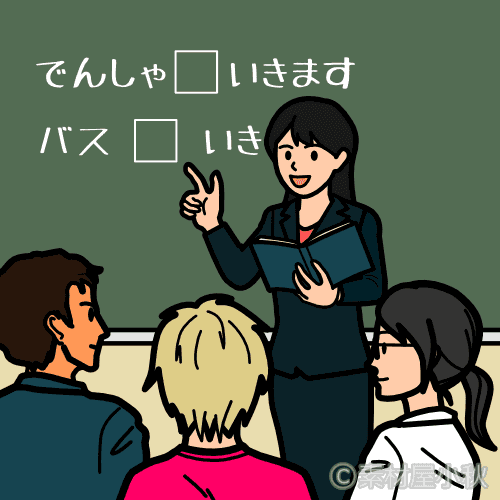 それらの話を聞いた上で、実際に日本語を勉強している学生さんの文章(テキスト)やスピーキングをグループに分かれて添削をしたり、て形とは何か、助詞「に」「で」(例:今日食堂「に」「で」食べました。)、助詞「は」「が」(例:だれ「は」「が」来ましたか。)の違いをどうやって教えるか?など、教え方を考えて説明をするという日本語教師を体験できる時間もありました!その体験を通じて、改めて普段私たちが話をしている「日本語」の難しさや奥深さを知ると同時に、今まで考えてもいなかった日本語のルールや発音を学ぶことで、日本語の新しい魅力に触れることができました。
それらの話を聞いた上で、実際に日本語を勉強している学生さんの文章(テキスト)やスピーキングをグループに分かれて添削をしたり、て形とは何か、助詞「に」「で」(例:今日食堂「に」「で」食べました。)、助詞「は」「が」(例:だれ「は」「が」来ましたか。)の違いをどうやって教えるか?など、教え方を考えて説明をするという日本語教師を体験できる時間もありました!その体験を通じて、改めて普段私たちが話をしている「日本語」の難しさや奥深さを知ると同時に、今まで考えてもいなかった日本語のルールや発音を学ぶことで、日本語の新しい魅力に触れることができました。
また、外国人の方と日本語を話す時にやってしまう「ありがちな対応」のお話は、目から鱗でした。例えば、相手が「すみません、わかりません」と言ってきた際に「あれ、難しすぎた?」のような独り言は、余計混乱をさせてしまったり、「どこに行きましたか。」「どこに住んでいますか。」の問いに相手が「?」となった時に「あ、どこに行ったんですか。」「どこに住んでいるんですか。」と質問の形態を変えてしまって、ますます難解にさせてしまうということがよくあるそうです。(「んですか」は日本人はよく使ってしまいがちですが、とにかく余計難しくさせているそうです!)
なので、上記のようなシチュエーションの場合は、簡単な文=「家はどこですか。」「出身はどこですか。」という(「XはYです」構文)を使ってあげることがベスト!とのことです。
最後に、冒頭で西村先生が日本語教師とは実際どんな職業なのかをお話された際に、「日本語教師は日本のことなら何でも知っていて、日本語の知識が豊富だと思われがちで、その為日々いろいろなことに注意して知識を貯えておく必要がある」こと、そして「言語は、文化だけではなく生き物なので、変化していきます。皆さんが今お友達と使っている日本語、それは今一番新しい日本語で、日本語教師の方々はそのような新しい日本語にも敏感でないといけない。」とおっしゃっていたことが印象に残っています。
(初級や中級では教えていないようですが、)例えば、日本に留学して帰ってくると、右上がりの口調で「これ、ヤバくね?」のような日本語も覚えてくるそうで、TPOで使い分けるように教えたり、日本の最新ドラマを授業で使用して「萌える」「レベチ」などという言葉についても説明をされているとのことで、アメリカに長年住んでいながらも、新しい日本語にも常にアンテナを張っていらっしゃって、
最高難易度である日本語をどのように学習者に興味をもってもらえるのか、どのように学生たちの知的好奇心をくすぐるのか、どうすれば楽しく、深く考えることができる題材になるのか、西村先生自身が「変化」「楽しむ」「面白い」を忘れずに教えていらっしゃるからこそ、日本語0から始めた学生が日本語がどんどん上手くなって、好きになって、最終的には日本語関係の教授になっていたり、日本の会社に就職していたり、そういった学生さんたちの成長を長年見てこられているのだな、と話を聞いていて思いました。
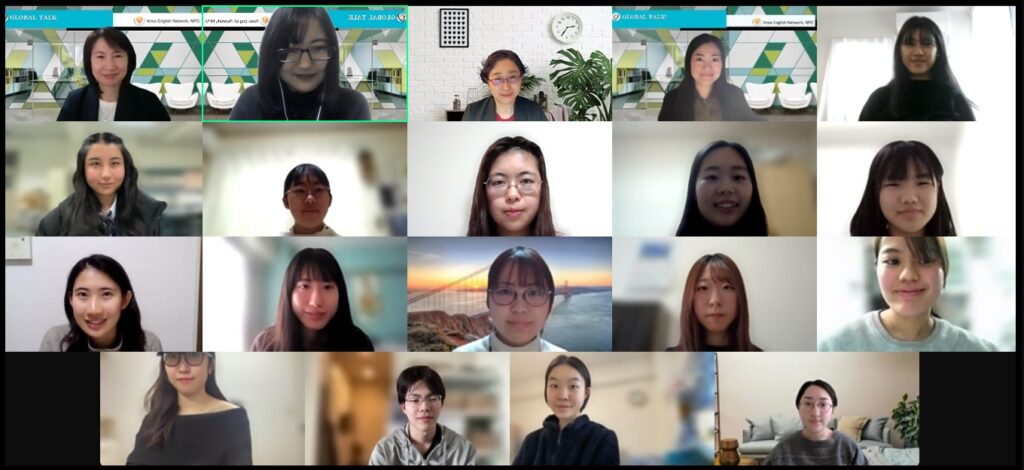 私にとっては、日本語教師の方から日本語を改めて教えてもらうということは、初めての体験でした。他ではなかなか聞けない貴重なお話ばかりで、率直に、まさか自分が生まれてきてから使っている日本語の新しい発見をこの歳になって発掘できるとは思ってもいませんでした!あっという間の楽しい時間で、西村先生のお話を聞く前と後では、視野が広がり、もっと深く日本語を知りたい、日本文化を学びたい、そして、英語を学ぶ上でも大切なことを学ぶことができました! 貴重な体験をありがとうございました!
私にとっては、日本語教師の方から日本語を改めて教えてもらうということは、初めての体験でした。他ではなかなか聞けない貴重なお話ばかりで、率直に、まさか自分が生まれてきてから使っている日本語の新しい発見をこの歳になって発掘できるとは思ってもいませんでした!あっという間の楽しい時間で、西村先生のお話を聞く前と後では、視野が広がり、もっと深く日本語を知りたい、日本文化を学びたい、そして、英語を学ぶ上でも大切なことを学ぶことができました! 貴重な体験をありがとうございました!



