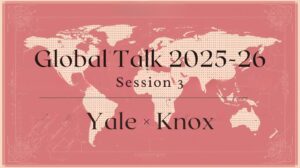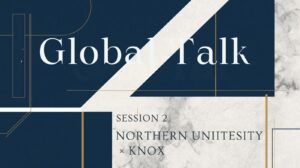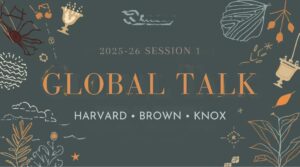ブラウン大学とのSession22では、さまざまな社会問題の中から一つのテーマを選び、ペアで協力して啓発ポスターやプレゼンテーションを作成する交流を行いました。
初回の全体交流では、プロジェクトの概要とともに、「コミュニティガイドライン」について説明がありました。そこでは、「お互いの背景を理解し、相手の意見を尊重する」「人の話を最後まで聞き、すぐに否定しない」「他の人の発言を外部に漏らさない」「話したくないことを無理に話させない」など、安全で安心して意見を交換できるセーフスペースをつくるためのルールが共有されました。こうした取り決めが交流前に示されるのは初めての経験で、とても新鮮に感じました。特に、立場や意見が分かれることの多い社会問題を扱ううえで、スムーズな議論を進めるためには不可欠な工夫だと実感しました。
この交流では、ペア同士の自主性が非常に重視されており、自分たちでスケジュールを立て、責任を持って活動を進める必要がありました。その分、異なるバックグラウンドを持つ相手と協働するという、とても貴重な経験ができたと思います。
私たちのペアが選んだテーマは「多文化共生」でした。日本とアメリカの両国における課題とその解決策を整理して発表することにしました。最終発表までにペアで話し合う機会が4回あり、それぞれの回で自国の現状について調べたことを発表し合い、質問を交わす形で交流を深めていきました。

日本における多文化共生の課題として、私は埼玉県川口市に住む在日クルド人をめぐる問題を取り上げました。川口市は外国人住民が非常に多い自治体であり、私の出身地でもあります。そこで発生している日本人と外国人とのトラブルや、クルド人コミュニティに対するヘイトスピーチの増加、SNS上での差別的な発言の拡散などを紹介すると、ペアのブラウン生も興味深く聞いてくれました。一方、ペアの学生はアメリカにおける多文化共生について、現地に住む視点から共有してくれました。現在、トランプ政権下で実施されている移民政策や、移民に対する偏見、また警察による人種差別的な対応や、メディアが移民の犯罪者に対して使う攻撃的な表現について話してくれました。彼自身も移民としてアメリカに移り住んだ経験があるそうで、現状についてのリアルな声を聞くことができ、とても学びが深まりました。
私たちはこの議論を通して、「外国人」や「移民」という言葉で個人をひとくくりにしがちであることに気づかされました。たとえば、外国人が事件を起こした場合、本来はその個人の問題であるにもかかわらず、その人が属する民族全体に対する偏見や差別が広まってしまうことがあります。こうした人種差別を助長するデマに惑わされず、ヘイトスピーチを許さない意識を持つことの大切さを確認し合いました。
ポスターやプレゼンテーションの作成においては、互いに助け合うことができました。特にスライド作成では、マイケルさんがデザイン面で大いに助けてくれ、私が気づかないうちに構成を整えてくれるなど、感謝の気持ちでいっぱいでした。私は日本語の表現や漢字の読みなどについてアドバイスできたと思います。それぞれの得意な分野を活かして補い合うことができました。
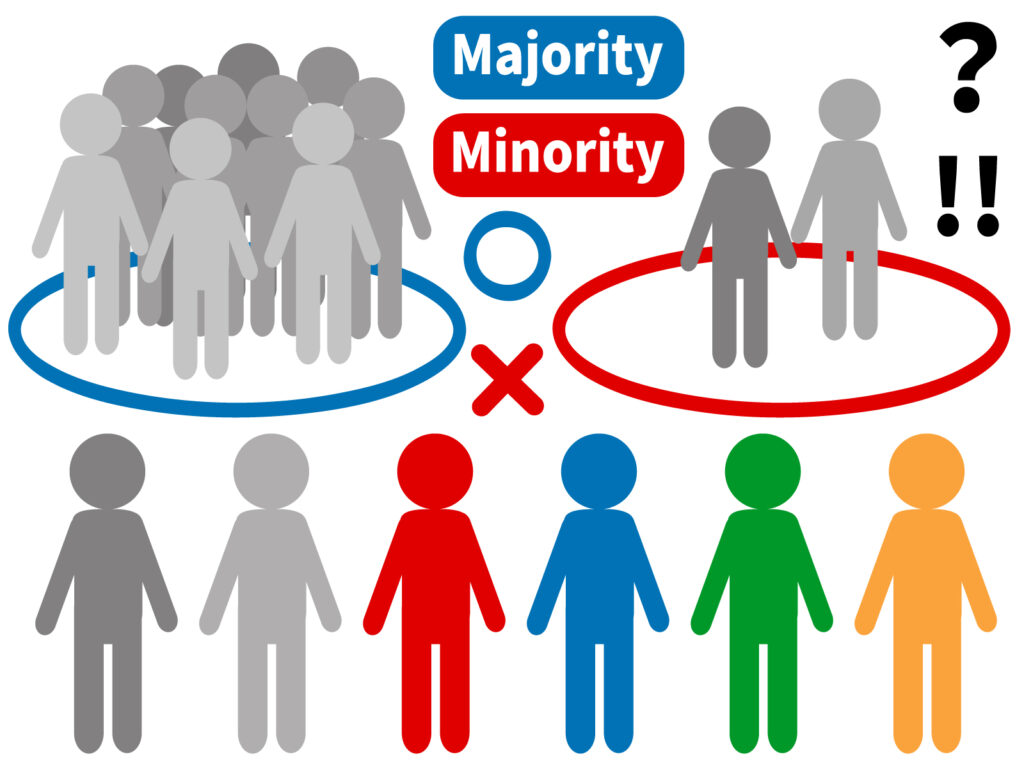
そして迎えた最終発表日。LGBTなど性的マイノリティを取り巻く問題、男女平等、聴覚障害者の災害時支援など、多様なテーマが取り上げられ、それぞれのペアが日米双方の視点から課題と解決策を提示していたのが印象的でした。どの発表からも、対話を通して協力し合いながら取り組んできた様子が伝わってきて、非常に心を動かされました。また、インターネットやメディアから得た情報だけでなく、自身の体験や身近な出来事に基づいた発表が多く、説得力があり、自然と引き込まれました。私自身の発表では、他言語である英語でプレゼンをする難しさを感じながらも、練習の成果もあり、自分の考えや経験がしっかり伝わったようで嬉しかったです。質疑応答では、私は日本語でコメントや質問をしましたが、ブラウン大学の学生たちは学習言語である日本語を使って質問をしており、その姿に感銘を受けました。私も、あらかじめ準備した内容だけでなく、その場で柔軟に英語を使える力を身につけたいと強く思いました。
このセッションを通じて、ペアの学生と協力して一つの作品を作り上げるという大変貴重な経験ができました。お互いが日本とアメリカという異なる国の現状を理解し、学び合えたことで、完成させた成果物の価値は非常に大きかったと思います。スケジュールを自分たちで管理しながら進めるのは大変でしたが、対話を重ねる中で日米の課題への理解を深めることができ、大きな達成感を得られました。これまで参加してきたセッションの中でも、特に充実した交流だったと感じています。この交流をきっかけに、今後も日本やアメリカが抱える社会課題に関心を持ち続けていきたいと思います。(M.K)