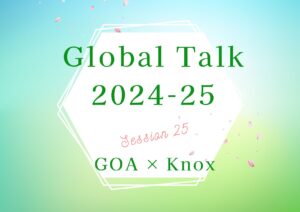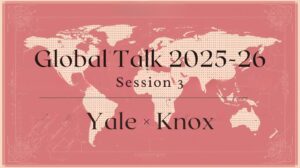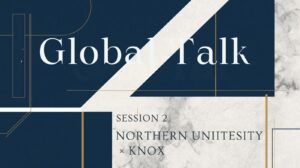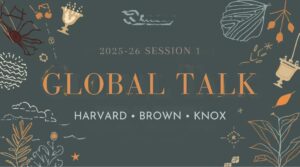今回は、Seesion30のご紹介です。Session30では、Brown大学の学生さんと協同でKnox生のトピックについて探求を行いました。Knox生が主体で探求を行うのが、このSession30の大きな特徴です!具体的には、以下のような流れで取り組みました。
研究トピックの決定
Knox生それぞれが自分の興味のあること(専攻・趣味・疑問など)をもとに、グローバルな視点を含むテーマを選びました。
実際のトピックは以下の通りです!それぞれ全く異なる分野で興味深いですね。
・ゲノム編集ー世界での規制・活用状況ー生命倫理と技術進歩のバランス、日本での市場・消費者意識、他国の現状、生態系への影響、国際的なルール作り、今後の食料問題の解決など
・建築、アート、そして地球 ー各国の建築やアートを見て、私たちが考えるべきこと、建築とアートの差異、建築やアートは創作者だけのものではないという具体的根拠、各国の建築やアートに対する姿勢・日本との違い、現在の地球環境から必要なこと、など
・特別支援教育一ESL一英語を第2言語とする児童の配属学級一日本とアメリカの差一
・不登校―日本の教育が抱える課題―日本と他国との比較―他国での不登校の現状やそれに関連する取組みなど
ペアワーク
研究トピックが決定すると、いよいよBrown生とのオンライン交流です!今年は、6週にわたって3人のペアと2回ずつ交流し、研究トピックを深掘りしました。それぞれ専攻や出身地などが異なるBrown生と交流できたこと、一人2回ずつ交流することでより深掘りできたことがとても有意義でした。
私自身、交流を進める中で、自分のテーマに改めて向き合ったり、ペアと話した中で得られた新たな視点から調べてみたりすることで、交流を重ねるごとに深められている感覚がありました。
ペアワークの一例として、私の活動をご紹介したいと思います!
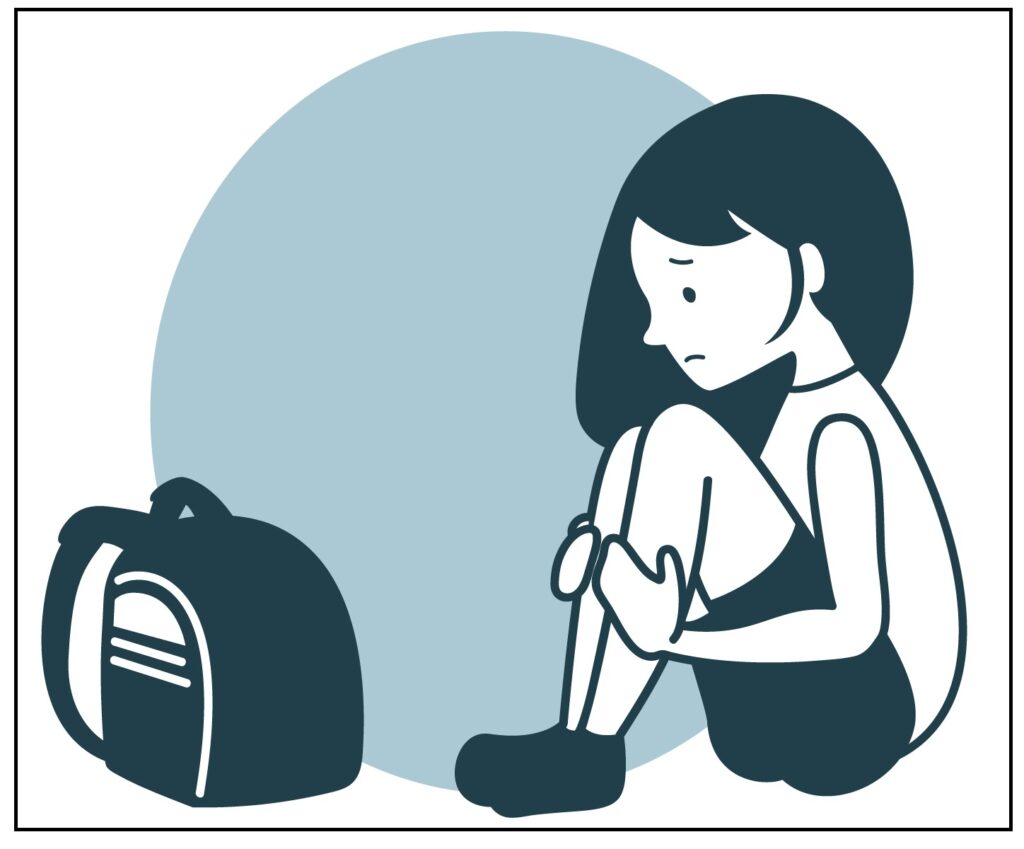 私の研究トピックは「不登校」についてです。ペアになった3人のBrown生がそれぞれ異なるバックグラウンドをおもちだったので、それぞれの経験についてインタビューすることを中心としました。不登校は世界的に珍しい現象なので、日本の中だけでこれまでは考えがちでしたが、ペアの皆さんの経験や意見を聴くことで、さまざまな違いや共通点を見つけることができました。具体的には、国によって教育システムやそれを取り巻く文化が大きく異なる中で、「不登校」について考えることの難しさを実感しました。例えば、日本では原則として学校に通わなければならないので、学校に通わない(通えない)不登校が問題と考えられます。しかし一方で、アメリカでは家庭によってさまざまな事情があることから、学校に行くことが必須ではない(ホームスクーリングなども認められている)のです。アメリカで不登校があまり問題になっていないのは、そもそも学校に通わないことが特別な現象ではないからか!と分かりました。このことから、不登校について比較するには、それぞれの国の教育システムや文化などについて理解を深めることから始める必要があると気づきました。
私の研究トピックは「不登校」についてです。ペアになった3人のBrown生がそれぞれ異なるバックグラウンドをおもちだったので、それぞれの経験についてインタビューすることを中心としました。不登校は世界的に珍しい現象なので、日本の中だけでこれまでは考えがちでしたが、ペアの皆さんの経験や意見を聴くことで、さまざまな違いや共通点を見つけることができました。具体的には、国によって教育システムやそれを取り巻く文化が大きく異なる中で、「不登校」について考えることの難しさを実感しました。例えば、日本では原則として学校に通わなければならないので、学校に通わない(通えない)不登校が問題と考えられます。しかし一方で、アメリカでは家庭によってさまざまな事情があることから、学校に行くことが必須ではない(ホームスクーリングなども認められている)のです。アメリカで不登校があまり問題になっていないのは、そもそも学校に通わないことが特別な現象ではないからか!と分かりました。このことから、不登校について比較するには、それぞれの国の教育システムや文化などについて理解を深めることから始める必要があると気づきました。
プレゼンテーション
 全てのペアワークを終えると、いよいよプレゼンテーションです!どのようにペアと探求を行ったのかや、ペアワークを通して得られた新たな気付きなどをスライドにまとめて発表しました。どの発表もペアワークを通して深掘りした研究成果を存分に伝えられていたと思います。
全てのペアワークを終えると、いよいよプレゼンテーションです!どのようにペアと探求を行ったのかや、ペアワークを通して得られた新たな気付きなどをスライドにまとめて発表しました。どの発表もペアワークを通して深掘りした研究成果を存分に伝えられていたと思います。
探求は各自で行われていたので、発表で初めて他のメンバーの研究について知ることができ、とても勉強になりました。さまざまなバックグラウンドを持つアメリカの学生と交流できることはもちろん、出身地や専攻などが異なる多様な日本の学生と交流できることも、このセッション、そしてGlobal Talkの魅力だなと再確認できました。
今回の探求を礎に、これからもそれぞれの研究や交流が深まっていくのではないかと思います。(Y.M)